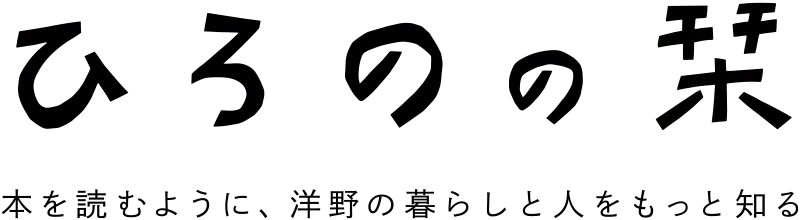【イベントレポート】洋野町風土性調査最終報告会
ー大切な風景を思うー

2025年3月1日(土)、ひろのの栞は洋野町風土性調査最終報告会を実施しました。この調査における風土とは「その土地の自然に、暮らしや生業を通して働きかけることで形作られる、私たちが生きる地域の環境」を指します。そして、風土性調査とは、風土の成り立ちを、地質・地形や気候、植生と生態系、人々の暮らし方などのそれぞれと、その相互の関係を調べながら解き明かしていくことです。今回は、2023年9月から続けてきた調査の内容と、その結果から考えられる洋野町の風土性について、環境デザイナーの廣瀬俊介さんより報告されました。本レポートでは、その内容を当日の流れに沿ってお伝えしていきます。
洋野町の大地の性質

小子内地区の海岸にて撮影した地層の様子
海と高原が広がる洋野町の地形は、全体にはなだらかで、大らかな印象を受けます。しかし、目を凝らすとその中にも 細かな地形の変化があることが見てとれます。沿岸部では、砂浜や礫浜のほか、崖と海が接している場所もあり、また内陸部には、久慈平岳などの山地、丘陵地があります。そのほかに氾濫平野や谷底平野が形成されている所もあります。
地質に目を向けてみると、洋野町には全体に花崗岩が広く分布しています。町の西側には玄武岩があり、東側の海沿いには、かつて海の底に溜まっていた砂が固まり岩となった砂岩があります。様々な地質が存在しますが、沿岸では、岩石の性質に関係なく、各時代に浅い海の底が波の力で平らにされ、大地の隆起と海面の変動によって順に陸地となった段状の地形である海成段丘が形成されました。洋野町の海成段丘のうち、標高約180〜300mの範囲に分布しているものは大野海成段丘と呼ばれ、最も古い九戸段丘(おおのキャンパス周辺など)は、現在の海岸線から約10km内陸側まで入り込んでいます。
このような地形/地質の違いの上に、やませなどの気候的条件が重なり、町内の各所に少しずつ地形/地質/土壌/水分/日照/風の吹き方といった性質が異なる環境ができました。このことは、洋野町に多種多様な植物が生育する理由として考えられます。
やませがもたらす気候条件

種市海浜公園から見たやませ
洋野町の気候の基本的な性質についても、ここで改めて確認をします。種市町史には「早春に乾燥した強い偏西風が吹き、フェーン現象により山火事が起こりやすい」と書かれています。また、春から夏にかけては「やませ」と呼ばれる霧を伴った冷たい風が太平洋から吹きつけてきます。大気に比べて温度変化の少ない海や、その海を例年晩秋から冬にかけて南下する対馬暖流などの影響もありますが、洋野町の気候は全般に冷涼といえます。
独特な植生

久慈平神社の近くで撮影したウメバチソウ
洋野町では、やませなどにもたらされる冷涼な気候によって、標高700m級の山でも高山植物が生育しています。本来さらに高い場所で育つはずの高山植物は、種市町史によれば町内で10種類以上発見されているそうです。このように、霧を伴うやませは、特徴的な植生を生み出した一方、日射を減少させ、これにより日中の温度上昇が妨げられるため、農作物は冷害を受けてきました。また、霧が作物に付着することによって葉の表面のガス交換や光合成が低下し、さらには炭水化物の流亡も引き起こされるため、これにより作物の成長が阻害されます。
高原との関わり

ひろのまきば天文台から見た高原
細やかに変化のある地形の上に冷涼な気候がもたらされている洋野町では、人々と自然の関係性はどのようなものであったのでしょうか。まずは、高原との関係性を見ていきます。
廣瀬さん:「洋野町の大地は、概ね平らですが緩やかな傾きを持ち、地面の傾きに沿って雨水や雪解け水は低い方へ流れます。地面に傾きがあるのは普通のことですが、洋野町では大きな面積を占める花崗岩に裂け目が生じやすく、そこから水が抜けやすいことがあって木が数多く生えるには至らずに草原ができる箇所が少ないと考えられます」
このような地域の地形・地質と植物の関係に合わせて、人々は牧畜を行ってきました。牧畜には、気候も密接な関わりをもっています。廣瀬さんは「草原が形成されやすい大地の性質と冷涼な気候に対応した土地利用が継承されてきているといえます」とも話されました。
海との関わり

マリンサイドスパたねいち付近の路地と、そこから見える太平洋
洋野町の海岸線には、干出岩盤地帯(干潮時に海上に露出する海食棚)が広がっています。潮が引いてしまうと岩盤が露出してしまうため、かつてはふのりやまつもなどの海藻類が一部で採取できたのみであったこの場所には、うにを育てるための増殖溝が設けられています。増殖溝の整備は、昭和50~54年度(1975~1980)、昭和57年度(1982~1983)に行なわれました。
廣瀬さん:「なかなか色々なものが育たない状況の中で、よく見ると『つぼ』と呼ばれる小さな潮溜まりには海藻が生えていることを漁師の方が発見されたのだそうですね。じゃあ、溝があるとさらに水の動きがあって良いのではないかということで、そういった観察に基づいて岩盤を一部削り、波のエネルギーを利用して海水を引き入れる方法を開発されたわけです。この例は、通常用いられる港湾技術に対比して、 自然に近しい土木技術ともいえるのではないでしょうか」
山や川との関わり

大野で撮影した花崗岩の岩肌
洋野町の大野では、製鉄が盛んに行われていました。そのときに原料となったのは、花崗岩が風化してできた砂から採取できる砂鉄です。ただし、「マサ」と呼ばれるその砂は砂鉄含有量が約1~3%と少なく、これを水に流しながら砂鉄だけを採取するため濁った水を発生させてしまい、問題になりました。その後、昭和14年(1939年)創業開始の川崎製鉄により画期的な発見がなされます。
廣瀬さん:「川崎製鉄により、マサがかつて海の底で溜まってできた層が発見されました。この『ドバ』という層は砂鉄含有量がおよそ40%あるということで、掘る土の量が少なくて済み、この方法が見つかってからは土地を大きく作り直す必要がなくなり、水をそれほど濁すこともなくなったのではないかという推定が、岩手県立大学の学生さんの研究論文に書かれています」
製鉄に必要な燃料には、赤松やコナラなどの山の木々が利用されました。これらの木々は、この土地で時折発生した山火事に対して強い性質を持っていました。
廣瀬さん:「コナラは、山火事で地上の部分が焼けてしまっても、根が生きていてまた芽が出てきます。赤松の方は熱に弱くて、山火事に遭うと枯れてしまうんですけれども、そうして一度荒れてしまった環境に種が飛んでくると今度は旺盛に生育しますので、山火事が起こりやすい場所に向いていました」
また、山の木々は大野木工にも利用されています。調査では、大野木工の製作や普及を引き継がれている方々にもお話を伺いました。この方々が考える山の木々の見方は、「山の木は、多種多様であった方が良い」というものでした。山の木々が本来的に多種多様であると、土が健全な状態になっていきます。そうすると、その土に養われた水がミネラルなどの栄養分を伴って山から川や海へ降りていく中で、流域の生物を生かし、成長させていくことに繋がります。そして農業を支え、漁業を支えていきます。
洋野町の風土を考える

この調査では、風土を「その土地の自然に、暮らしや生業を通して働きかけることで形作られる、私たちが生きる地域の環境」と定義しています。ここまで確認してきたような洋野町の自然条件や人々の暮らし方から、洋野町の風土性とはどのようなものであると言えるのでしょうか。
廣瀬さん:「洋野町の風土の基本的な性質は、特に大地の生い立ちに焦点をあててみて、『海から生まれた大地』という言葉で表わせるのではないかと考えています。地質から見ていくと、久慈平岳より西側の地質は、遠洋の海底を作る玄武岩とチャートという岩を中心に構成されています。チャートは遠洋の深海でプランクトンの死骸が固まってできました。そして、玄武岩等々が先にできていて、その後マグマが固まってできた花崗岩が隆起してきています。町の広い範囲を占めているのが、この花崗岩です。海側の方では、浅い海の底に溜まった土砂が固まってできた砂岩が花崗岩の上にかぶっています。このように、町の花崗岩類を除く岩石は海底でできています」
地形に関しては、花崗岩類を含めて、海底であった時期に波に洗われて平らになっています。海成段丘の分布をみると、かつての海岸線が現在の海岸線とほぼ平行に階段状に並んでいる地形であることがわかります。
廣瀬さん:「そういった大地の上で展開される気候というのがやませです。やませは、三陸沖で暖流上の低気圧と寒流上の高気圧の間に生じた西に吹く風が、北のオホーツク海から降りてくる冷たく湿った空気を陸側に吹き寄せて発生します。やませは、人間が暮らす上では大変なんですけれども、独特な自然条件を作っています。こうした中で、種市町史編纂委員の酒井久男さんの「ひろのの栞」への寄稿 「過去は未来への道しるべ」にあるように、洋野町で、人々は、厳しい状況のなかで一生懸命考えながら、あるいは考えることを諦めない精神性を保ちながら、それを引き継いできているといえるのではないでしょうか。大まかには、洋野町はそのような風土性を有する町だと思います」
最後に、今後の課題として廣瀬さんは「地形や河川流域、集落分布と街道の関係の図解」に取り組んでいくことの必要性について言及し、それにより、地区ごとの特徴や個性をとらえやすくなり、洋野町の歴史と未来が生き生きと見えてくるのではないか、と述べられました。
ワークショップの様子

今回のワークショップも、第2回中間報告会のときと同様にグループワークで行いました。今回のテーマは「大切にしていきたい風景」で、具体的には、以下のような流れと内容でした。
1.一人ひとりの「大切にしてきたい風景」について話す
2.「その風景に対して自分がなにかできることがあるか/その風景がどうなってほしいか」という問いをきっかけに話し合う

ワークショップで配布した資料
各テーブルには、話し始めるきっかけとなるように、洋野町の地図と写真を配布しました。写真は、前回のワークショップで、参加者から「思い出や愛着のある風景/場所」としてお話しいただいた地点を筆者が訪れ、撮影したものです。
今回もみなさまから、町内の様々な場所の風景についてお話しいただきました。その中から一部をご紹介いたします。
・テレトラックたねいち付近の国道45号線から見る、種市病院と役場と太平洋と街並み(朝焼け時)
・種市のまち通り(映画館、せんべい屋さん、おうめい館、旅館) 魚屋さん(良い香りがした)
・大野館址から街をのぞむ(久慈平岳)
・大正寺「来迎山」 なくなった風景 香り
・全体的に森林の保全が大切
参加いただいた方のアンケートより
アンケートは、50代から80代の計16名にご回答いただきました。ありがとうございました。アンケート結果について共有いたします。
●報告会で最も印象に残った内容は何でしたか。
・大野の地形の成り立ち
・気候と地形・地質となりわいのかかわりがよく分かる内容でした。
・内容もですが参加者の皆さんが洋野の事を想う気持ちが強く感心も高い事が今後につながると思った。
・続けられてきた生業が地形の理にかなっているということに安心感をおぼえました。
・あらためて町の風景を考えさせられましたし、思い出としてあふれた話し合いが良かった。
●見慣れた風景の中で少し気になっていることについての質問や、「こんなことを調べてみてはどうか」といった情報提供があれば、お書きください。
・海藻が減っていること
・周辺の市町村との関連(地質、気候、人的交流等)
・6~7割を占める森林の力や、資源としての樹林の活かすことをもっと地域全体で意識していきたい。
・今では淋しくなった町なみ(商店街)、でも写真は残っている。古家にあるアルバムから発掘してみてはどうか?
・縄文遺跡の分布と地域資源としての活用について
アンケートの紹介は以上になります。
風土性調査を終えて
2023年の9月から、およそ1年半にわたり実施してきた風土性調査が、一つの区切りを迎えました。今回わたしたちは、春夏秋冬、各季節ごとの洋野町の風景を見てまわりました。
そこで出会う風景は、自分自身の地元でありながら知らないものが多く「今日はどんな風景が見られるだろう」との期待を持ちながら調査に同行していました。そして、段々と植物の名前や地形などについて実感をもてることが増え、普段見ている景色の見え方が変わっていきました。そのような中で考えるようになったのは「洋野町の姿とはどんなものであるだろう?」ということです。町に暮らす人、町に広がる風景、それぞれの要素がつながり合って浮かび上がってくる「洋野町の風土」とは、どんな姿なのだろう、と考えるようになりました。
報告会の最後に廣瀬さんは、洋野町の風土の基本的な性質を「海から生まれた大地」と表現されました。それは、洋野町には、海と、海から生まれた大地と、海に由来する大きな気候があり、それにより独特な環境が育まれ、そしてこの土地に暮らす人々は、当地の自然環境を注意深く観察し、対峙しながらなりわいを営んだきた、というようなことでした。
自分が感じてきたこと、それらが「海から生まれた大地」という言葉でつながるような感覚がありました。また、私たちがこの調査で明らかにしようとしていた「洋野町らしさや町の魅力を支えるもの」の形が、少しですが見えたように思えます。
ですが、まだまだ知らないことがあります。だから私たちは、町の風景に目を向け、そこにあるものに思いを巡らせ、「何」が「どうして」大切なのか考えることを続けていこうと思います。
最後になりますが、この調査は、聞き取り調査や資料の提供にご協力くださった方々、報告会にご参加いただき貴重な意見を話してくださった皆さまなど、多くの方々のご協力がありここまで進めることができました。本当にありがとうございました。この調査を元にした新たな展開がある場合には、ひろのの栞でお知らせいたします。また、最終報告書のPDFデータは無償で提供いたしますので、ご希望の方はお問い合わせください。報告書を印刷したものは町内の図書館でお読みいただけます。営業日や開館時間などをご確認の上、ご利用ください。
発表者
環境デザイナー 廣瀬俊介さん
環境デザイナー、専門地域調査士(日本地理学会)、風土形成事務所主宰。LLP風景社組合員。2014年まで東北芸術工科大学大学院准教授。著書に『風景資本論』(朗文堂、2011年)など。地理・生態・民俗学ほかの知見をもとに、地域の持続のための環境計画・設計を行う。
(2025/05/07 レポート 藤森大将)